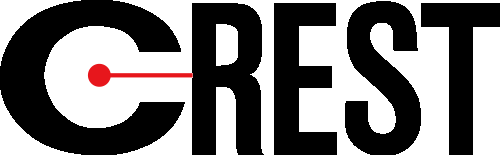伝わる言葉
社内の本棚で見つけた『日本語と外国語』(鈴木孝夫氏)という、紙が少し黄ばんだ新書を読んでいる。1990年に第1版が出ているものだ。
第1章では日本語と外国語のそれぞれの表現やしくみ(言葉の叙述機能、描写機能)が文化によって違うことを興味深い具体例を挙げて説明している。
こんな感じだ。
- 日本語では長靴でも短靴でも同じ靴だが英語ではbootとshoeは全く別物。
- 日本語のはきもの(履物)は足袋や靴下は入らないが英語のfootwear(footgear)には靴、長靴、スリッパ、靴下まで入る。
- 英語でオレンジ色の車、オレンジ色の猫は日本では茶色にあたる。
- リンゴは日本では赤いリンゴを思い浮かべるが、フランスでは緑。
- 太陽は日本やロシアでは赤く、欧米では黄色い。月は太陽が赤ければ黄色いが、太陽が黄色であれば白。
- 英語、日本語では蝶と蛾は別の言葉があるが、フランスやドイツは1つの言葉で包含している。フランスの百科事典には蝶と蛾が混ざった写真が掲載されている。
「一つの国の文化というものは、このように一度それと分かってしまえば何でもないことに、当人が自覚していない極く小さな暗黙の社会的なとりきめやきまりが無数に含まれている。」
まさにその通りだ。
「この部分が、いわば文化の根ともいうべき基層を形成して」いるそうだ。
その事例として挙げられているのが日本の大手食品企業がイスラム圏に缶詰を輸出したエピソードだ。
現地でも目隠し調査では評判がよかったにも関わらず、缶詰はさっぱり売れない。
原因は缶詰のパッケージに太陽の印があったから。イスラム圏では暑さをもたらす太陽は最も不愉快でマイナスなイメージ、それが缶詰のイメージになっていた。
太陽が沈むと砂漠は突如として涼しくなる。そこに現れる月こそ美であり救いであり希望となる。イスラム圏で三日月(新月)を国旗に取り入れている国が多いのはそのためだそうだ。
これは太陽の印(イメージ)のエピソードで「言葉」の問題そのものではない。しかし文化圏の違う人にとって、そのイメージを示す「太陽」や「月」という言葉は全く違う意味で捉えられてしまうことがよくわかる。
文化の違いで言葉の表現やしくみはこんなにも変わる。それは時には対立や衝突をもたらす。言葉というものの重さは計り知れない。
たとえ、同じ文化を持つ同じ国の人間だったとしても、生まれ育った地域や世代、性別で言葉の意味や受け止め方は変わるものだ。
例えば「ヤバい」という話し言葉は「危険な」「まずい」「都合が悪い」といった意味で使われるが、若年層は「すごい」「素晴らしい」「かっこいい」といった肯定的な意味で使うようになってきている。
だからこそ、マニュアル作成では言葉を大切に選んで紡いでいくことを忘れてはならないと感じている。
我々が作成する企業のマニュアルは、基本的に言語を同じく*する一つの会社の社員を対象に限定した利用者のものだ。(*:日本語で作成したマニュアルを海外支店用に翻訳して提供することもある)
マニュアルは文学作品ではないし、話し言葉もマニュアルには登場しないから、言葉による表現を気にする必要などあるのかと思われる人もいるだろう。しかし、誰にでも間違いなく伝わるような、「すんなり読めて」「わかりやすい」ものにするための努力は必要だ。
そのための観点は次のようなことだ。
- 一つのものを指す言葉を様々な言葉で表していないか(用語を統一して使っているか)
- 利用者の立場に沿った文章であるか(システム側を主体に書いていないか)
- 一文がダラダラと長くなっていないか(短い文章に区切れないか)
- 修飾語と被修飾語の位置が離れすぎていないか(意味がわかりにくくないか)
- 利用者(読み手)によって違う意味にとられないか
明確で正しい言葉を使って、シンプルな文章を作る。
これこそマニュアル作成に必要な技術かもしれない。
利用者に、「マニュアルを読むのは大変」という気持ちにさせないマニュアル。「読んだ」「読まなきゃ」と思わせないマニュアル。「文章を読む」ということを意識させずに「目を通したら仕事が理解できた」位のマニュアルを作れないだろうかと奮闘する毎日である。